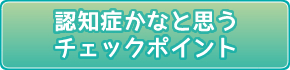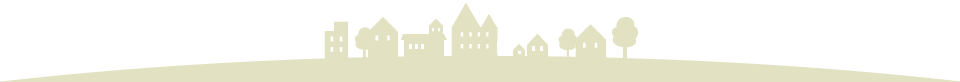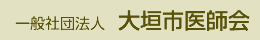ホーム > 認知症とは
認知症とは
身近な問題「認知症」 自分は大丈夫と安心していいの?
認知症は高齢化が進むにつれて急増しています。
わが国の認知症の高齢者の数は、2012年には約305万人といわれていたが、2013年の厚生労働省の発表では、462万人といわれています。
わが国では65歳以上の7人に1人85歳以上では、約3人に1人が認知症といわれています。
認知症は高齢者に多くみられますが、64歳以下で発症することもあります。
このような若年性認知症の人は約37,800人と推計されています。
認知症は高齢になればなるほど、発症の危険は高まります。
認知症は、決して特別な人がかかる病気ではありません。
誰にでも起こる可能性があります。
「ご自分やご自分のご家族には関係ない」と考えず身近なこととして、まずは関心を持ちましょう。
介護する側、あるいはされる側として、だれもが将来、認知症という病気に関わる可能性は十分あると言えます。
認知症はひとごとではないのです。
わが国の認知症の高齢者の数は、2012年には約305万人といわれていたが、2013年の厚生労働省の発表では、462万人といわれています。
わが国では65歳以上の7人に1人85歳以上では、約3人に1人が認知症といわれています。
認知症は高齢者に多くみられますが、64歳以下で発症することもあります。
このような若年性認知症の人は約37,800人と推計されています。
認知症は高齢になればなるほど、発症の危険は高まります。
認知症は、決して特別な人がかかる病気ではありません。
誰にでも起こる可能性があります。
「ご自分やご自分のご家族には関係ない」と考えず身近なこととして、まずは関心を持ちましょう。
介護する側、あるいはされる側として、だれもが将来、認知症という病気に関わる可能性は十分あると言えます。
認知症はひとごとではないのです。
加齢による「もの忘れ」と「認知症」の違い
誰でも年をとると、体の動きや内臓が衰えます。同じように脳の働きも若いころのようにはいかなくなり、年齢相応の“もの忘れ”がみられるようになります。これは自然な老化現象です。
一方、認知症は脳にあきらかな障害が出現する病気です。
一方、認知症は脳にあきらかな障害が出現する病気です。
| 加齢によるもの忘れ | 「認知症」によるもの忘れ | |
|---|---|---|
| 忘 れ 方 |
出来事の一部を忘れる (例:食事で何を食べたか忘れる) |
出来事の全体を忘れる (例:食事したこと自体を忘れる) |
| 自 覚 |
もの忘れをしている自覚がある (思い出そうとする・ヒントがあれば思い出せる) |
もの忘れをしている自覚がない (「まだ食べていない」「食べさせてくれない」) |
| 日 常 生 活 |
支障はない | 支障がある |
| 進 行 |
あまり進行しない | 進行していく |
| そ の 他 の 症 状 |
なし |
など
|
注:この表はあくまでも目安です。もの忘れが気になったら早めに受診することをお勧めします。 |
||
早期に専門医の受診をすすめる理由
早期発見、早期診断をして早期に適切な対応をすることは大変重要です
- 病気の確定
本当に認知症なのか、症状が似ている他の病気なのかをはっきりさせるとともに、
認知症を引き起こしている原因は何かを見極めることにより、的確な診断ができ、治療の方針が立てられます。認知症の進行を遅らせたり、症状を緩和することで、
ご家族と一緒に過ごす時間を長くすることができ、
またご家族、介護者の負担を軽くすることができます。 - 病気を理解する
専門医から今後の病状についての見通しを聞くことで、ご家族や親戚が介護体制について相談したり、介護環境を整える準備ができます。 - 介護への道が開ける
専門医の診断を受けて、病気について説明してもらうことによって、現状を受け入れる気持ちが生まれ、対応の仕方などアドバイスを受けることもできます。
認知症という病気を理解しないまま介護を続けていると、
症状がさらに進んでしまったり、ご家族との関係が悪化してしまうこともあります。
症状がさらに進んでしまったり、ご家族との関係が悪化してしまうこともあります。
| 出典: | 岐阜県認知症疾患医療センター(大垣病院内) 「認知症ってどんな病気?」 |
| 参考: | 朝田 隆ほか 厚生労働科研究費補助金認知症対策総合研究事業 「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」(2013) |